学会企画
第136回大会における学会企画
北海道大学で開催される第136回日本森林学会大会では、学会本部が中心となって以下の5つのイベントを開催いたします。
- 学会企画1.ランチョンミーティング「困りごとを共有しよう!改めて、選択的夫婦別姓制度の必要性を考える(3/21)
- 学会企画2.帰国留学生会員およびアジアの森林学会との国際交流会・Online Reunion of Ex-Overseas Student Members and International Networking Forum among Forest Societies in Asia(3/21)
- 学会企画3.JFRのData Noteに投稿しよう!(3/21)
- 学会企画4.第12回高校生ポスター発表表彰式 および 高校生対象の大学ツアー(3/22)
- 学会企画5.日林誌の使い方(3/22)
学会企画1.ランチョンミーティング「困りごとを共有しよう!改めて、選択的夫婦別姓制度の必要性を考える
コーディネータ:
佐藤 宣子(ダイバーシティ推進担当理事,九州大学)
村上 拓彦(同主事,新潟大学),ダイバーシティ推進委員会
日時・会場:
3月21日(金)12:00-13:00 会場:N21
※対面開催/ライブ配信なし/録画公開なし
内容:
国連の女性差別撤廃委員会は日本政府に2024年10月29日に、異例の4回目となる選択的夫婦別姓制度の導入を勧告しました。日本は別姓を認めない唯一の国となっており、国際的な活躍が求められる研究者が困っていることを共有し、発信することが求められています。日本森林学会は男女共同参画学協会連絡会の23期幹事を担っています。2025年秋開催予定の第23回男女共同参画学協会連絡会シンポジウムでは「選択的夫婦別姓」をテーマとする予定です。森林学会大会においても「選択的夫婦別姓」の必要性について考えるきっかけを設けたいと考えました。2名の方々からの話題提供を交えて会員各位と意見交換できる場としたいと思っています。お弁当を食べながら気楽に情報交換しませんか?
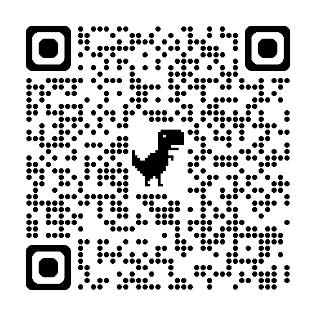
★参加申込不要・参加費無料
お弁当&お茶(500円)のみ要予約(3月9日(日)締切)右のQRコードから→
プログラム:
12:00 開会挨拶/趣旨説明
佐藤宣子(九州大学)
-話題提供-
「学生時代に旧姓名使用で困った!」
小川 結衣(筑波大学)
「インドネシア政府からの調査許可取得で困った!」
志賀 薫(森林総合研究所)
フリーディスカッション
13:00 閉会
問い合せ先
ダイバーシティ推進委員会(diversitypromotion<at>forestry.jp)

学会企画2.帰国留学生会員およびアジアの森林学会との国際交流会・Online Reunion of Ex-Overseas Student Members and International Networking Forum among Forest Societies in Asia
コーディネータ:
中静透(国際交流担当理事,森林総研)国際交流推進委員会
大久保達弘(東北農林専門職大学),大田真彦(長崎大学),
藤原敬大(九州大学),板谷明美(三重大学),櫃間岳(森林総研)
Nakashizuka Tohru (Director of International Exchange, Forestry and Forest Products Research Institute)
International Exchange Promotion Committee: Ohkubo Tatsuhiro (Tohoku Professional University of Agriculture and Forestry),
Ota Mashiko (Nagasaki University), Fujiwara Takahiro (Kyushu University),
Itaya Akemi (Mie University), Hitsuma Gaku (Forestry and Forest Products Research Institute)
日時・会場:
ポスター発表 全日・ウェブ配信
国際交流会3月21日(金)17:00-19:00 会場N31
対面・オンライン配信/録画公開なし
Poster Presentations: All days through an asynchronous (on-demand) format
Networking Meeting: March 21 (Fri) 2025, 5:00 PM – 7:00 PM (GMT+9) (the time is subject to change)
内容
日本森林学会には,多数の留学生が学生会員として所属し,発表を行なっている。しかし,会費負担等の関係から,帰国後は本学会を退会し,関係が疎遠になる場合が多い。
本企画では,再開された対面開催にオンラインを加えたハイブリッド形式のメリットを生かし,すでに本国に帰国した元留学生会員への学会参加・発表機会を提供する。目的としては,学位取得後の研究フォローアップ,学会発表実績の提供および帰国留学生会員同士や日本人会員との国際共同研究の萌芽形成を想定している。
参加者から事前に提出されたポスター発表を,学会の全日程,非同期(オンデマンド)形式で公開する。これに加え,本企画では,対面とオンラインのハイブリッド形式で国際交流会を行い,参加者同士が直接やりとりできる機会を提供し,今後の交流に向けた意見交換を予定している。アジア各国の林学会(韓国,中国)からの活動内容の紹介も含む予定である。現在日本の大学に所属している留学生会員や日本人会員にも,積極的に参加して頂きたい。
必要事項(参加者氏名・身分・所属先・メールアドレス)を,期日(3月20日(木))までに担当者(大久保達弘(Ohkubo Tatsuhiro))あて(okubotat<at>tpuaf.ac.jp)までお送りください。こちらからオンラインアドレス(ZOOM)をお送りいたします。
There are many active international student members in The Japan Forest Society. However, due to the burden of membership fees and other factors, many of them withdraw from the Society after returning to their home countries, and the relationship with the Society often becomes estranged. The purpose of this project is to provide an opportunity for former international students who have already returned to their home countries to participate in the conference and make presentations, using online methods. The purpose of this event is to follow up their research after obtaining their degrees, to provide them with an opportunity to present their research at academic conferences, and to form the seeds of international joint research among former international student members and with Japanese members.
The poster presentations submitted in advance by the participants will be opened to the public on site and an asynchronous (on-demand) format during the entire meeting. In addition to this, we plan to hold an exchange meeting in a hybrid format (on-site and synchronous (real-time) online) to provide an opportunity for participants to communicate directly with each other and exchange opinions for future exchanges. And also we plan to include an introduction of activities from forestry societies in Asian countries (South Korea and China). We hope that international and Japanese members who currently belong to Japanese universities will actively participate in the meeting.
If you would like to participate in the networking meeting in a synchronous (real-time) online format, please send the required information (participant’s name, status, affiliation, and e-mail address) to Dr.Ohkubo Tatsuhiro (okubotat<at>tpuaf.ac.jp) by the deadline (March 20 (Thu), 2025). We will send you the web meeting (Zoom) address.
学会企画3.JFRのData Noteに投稿しよう!
コーディネータ:
溝上展也(JFR担当理事, 九州大学)
志水克人(JFR担当主事, 森林総研),町田庸子(JFR編集事務局, 学会誌刊行センター)
日時・会場:
開催日時:3月21日(金) 17:30~18:30 会場:N13
対面開催/ライブ配信(オンデマンド配信予定)
内容:
Journal of Forest Research (JFR)では2024年6月から新しい原稿種別としてData Note(データペーパー)を導入し、投稿を受け付けています。しかし、分野によってはデータペーパーに馴染みがなく、どのような原稿が掲載に適するかわからないといった意見もあります。本企画ではJFRでのData Noteの審査基準と方針を説明し、データペーパー出版のメリットや具体例について話題提供します。
科学技術基本計画でオープンサイエンスの推進が謳われ、2024年2月には「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」が策定されました。この方針により、公的資金のうち2025年度から新たに公募を行う科研費等の競争的研究費の受給者に対して、「学術論文及び根拠データの学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤へ掲載(即時オープンアクセス)」することが義務付けられます。これまで、塩基配列やタンパク構造、さらには画像情報など、基礎生物学分野での論文公開に伴うデータ登録は広く普及してきましたが、日本の森林関連のフィールドデータについてはこれからの状況であり、Data Noteの発展が期待されます。そこで本企画では、Nature姉妹紙の「Scientific Data」の編集委員でもある久米篤氏に「オープンサイエンス時代におけるフィールド研究データの公開戦略」についての基調講演をしていただきます。
多くの分野の会員がリポジトリにデータ登録しJFRにデータペーパーを投稿するまでの疑問を解消できるように議論を深めましょう。
プログラム
司会:志水克人(JFR主事)
(1)基調講演「オープンサイエンス時代におけるフィールド研究データの公開戦略」
久米篤(Scientific Data編集委員)
(2)「Data Noteの編集方針と審査基準」 溝上展也(JFR編集委員長)
(3)総合討論
学会企画4.第12回高校生ポスター発表表彰式 および 高校生対象の大学ツアー
コーディネータ:
太田祐子(中等教育連携推進担当理事,日本大学)
佐橋憲生(中等教育連携推進担当主事,日本大学)
大平 充(大会運営高校生ポスター発表担当,北海道大学)
開催日時:
3月22日(土) 表彰式14:15~15:00 会場:学術交流会館 小会室
対面開催/オンライン配信(関係者のみ)
大学ツアー15:00~16:00(高校関係者・希望者のみ)
対面開催/配信なし

内容:
高校生ポスター賞受賞校の発表と表彰式を行います。申し込みは不要です。
表彰式終了後に希望者を対象に「高校生対象の大学ツアー」を実施します。
大学生が研究室や研究施設などを案内します。希望者はQRコードよりお申し込みください。
申し込みは右のQRコードから→
表彰式および大学ツアーのスケジュール
14:15~15:00 表彰式(森林学会会長からの総評)
15:00~16:00 高校生対象の大学ツアー(オプション)希望者のみ
高校生ポスター発表学校名・発表題目
| 発表番号 | 学校名 | 発表題目 |
| KP-01 | 北海道士幌高等学校 | 地域環境を繋ぐ・支える・育む 防風林造成 |
| KP-02 | 北海道帯広農業高校 | 帯広農業高校学校林の再造林の取り組みPart2 |
| KP-03 | 北海道標津高等学校 | サトウカエデ樹液の流出と温度の関係および濃縮後のメープル シロップの調査 |
| KP-04 | 北海道富川高等学校 | 日高山脈襟裳十勝国立公園に関する研究 |
| KP-05 | 宮城県仙台第三高等学校 | 仙台三高「時習の森」林冠ギャップが森林内に与える影響 |
| KP-06 | 栃木県立矢板東高等学校 | 木質バイオマス発電を活かした未来とまちづくり |
| KP-07 | 群馬県立尾瀬高等学校 | 尾瀬国立公園におけるニホンヤマネ調査2024 |
| KP-08 | 群馬県立尾瀬高等学校 | 尾瀬高校周辺のチョウ類調査 |
| KP-09 | 東京都立国分寺高等学校 | 音声からカラスバトの情報を探る |
| KP-10 | 東京都立国分寺高等学校 | GPS発信機を使ったカラスバトの生態調査 |
| KP-11 | 東京都立科学技術高等学校 | 香りによる植物のコミュニケーション |
| KP-12 | 中央大学附属高等学校 | 多摩丘陵におけるムササビの分布と森林環境 |
| KP-13 | 神奈川県立厚木高校 | デンプンの種類が微生物発電に与える影響 |
| KP-14 | 神奈川県立吉田島高等学校 | 矢倉沢演習林から発信する地域の未来 |
| KP-15 | 石川県立七尾高等学校 | 対峙培養法におけるヒラタケとカビの成長範囲変化 |
| KP-16 | 岐阜県立加茂農林高等学校 | 外来樹種を活用したキノコ栽培について |
| KP-17 | 不二聖心女子学院高等学校 | 不二の杜 ~みんな集まれ!! 学校がフィールドプロジェクト~ |
| KP-18 | 不二聖心女子学院高等学校 | 持続可能な学び舎~みんな集まれ!!学校がフィールドプロジェクト~ |
| KP-19 | 京都府立北桑田高等学校 | 京都フォレストスタイル~森林資源の循環~ |
| KP-20 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 金剛山における、手入れの優先度のヒートマップ作成~森の健康診断を用いて~ |
| KP-21 | 山口県立大津緑洋高校大津校舎 | 楽器を通じて国産材の認知度向上へ挑む |
| KP-22 | 高知県立高知農業高等学校 | 森林3次元計測システムを利用した森林資源情報のデジタル化に向けた取組 |
| KP-23 | 長崎県立長崎東高等学校 | 里山高齢林における伐採後10年間の炭素蓄積量の変化 |
| KP-24 | 熊本県立矢部高等学校 | ニホンミツバチに関する研究 ~地域と連携した魅力発信の取組~ |
| KP-25 | 熊本県立矢部高等学校 | 林業のちから×ふくしの心~林福連携ですべての人に健康と福祉を~ |
| kP-26 | 熊本県立南稜高等学校 | 小馬床演習林における森林保水力の調査及び流域治水スタディーツアーの実践 |
| KP-27 | 熊本県立南稜高等学校 | 人吉・球磨地域の豊かな森林資源の活用で地域活性化 |
| KP-28 | 沖縄県立球陽高等学校 | 沖縄地域樹種の種子オイル抽出と化粧品応用に向けた可能性の検討 |
国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」助成事業/大日本山林会協賛 中等教育連携推進委員会
学会企画5.日林誌の使い方
コーディネータ:長池卓男(日林誌担当理事,山梨県森林総合研究所)
開催日時:3月22日(土) 15:15~16:15 会場:N31
内容:
森林科学の広い分野を対象とした和文誌である日林誌。107巻を迎え、「もっと使う・使われる日林誌」のきっかけになればと、「日林誌の使い方」を企画しました。
日林誌では、日林誌に掲載された論文の根拠データ等について、J-STAGE Dataで公表できます。2023年10月に公表された「公的資金による学術論文等のオープンアクセスの実現に向けた基本的な考え方」にあるように、根拠データの公開が求められるようになっています。担当編集委員より、J-STAGE Dataのアップロードから公開までの流れや、公開データの現状およびその使われ方等についてお話しします。
また、会員の皆さんが講義、講演、行政資料等で日林誌をどのように使っているのかを募集し、日林誌の使われ方についてお伝えします。
プログラム:
1.日林誌の現状と課題 長池卓男(日林誌編集委員長)
2.J-STAGE Dataを使ってみよう! 北原文章(日林誌J-STAGE Data担当編集委員)
3.日林誌の使われ方 長池卓男
